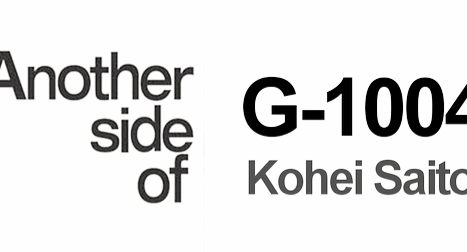April 30
自宅から歩いて10分程度のTD Garden。そこでついにNBAの試合、Boston Celticsのホームゲームを観戦する。入場可能な観客数はキャパシティの12%までということで、用意される客席数も多くなく、よって入手できるチケットもだいぶ高額ではあるが、この日は対戦相手がSan Antonio Spursというこれまたわたしの好きなチームだったこともあって、生観戦を決意。
緊張しながらTD Gardenへ。と言っても、普段買い物に来るスーパー Star MarketはTD Gardenの地下なので、歩いているのはいつもの道にすぎないのだ。日々卵や玉ねぎやバドワイザーを買っている建物に、Jason Tatum や DeMar DeRozan などのスター選手たちがいるというのは、奇異でもある。入場するには、COVID-19対策のためヘルスチェックが必須なのだが、ただ単に「ヘルスチェックをしました」という画面をiPhoneで見せればそれでOKというところがやっぱりアメリカ。観戦中のマスク着用は義務なのだが、みんな何かしらお酒やジュースなどのドリンクを飲んでいるし、観戦中は野次や声援も飛ばしに飛ばしている。「マスクをしてください!」と注意をするスタッフのおじさんを周りのお客さんと一緒に「Sorry マスクマン!」とからかって一旦だけこれ見よがしにマスクで顔を覆ってみせる…そんな人が多いのも(お行儀がかなり良い都市ボストンとはいえ)やっぱりアメリカ。
試合のほうは、第2Q終了時点で、CelticsがSpursに30点差をつけられて負けている、という Celtics ファンにとっては最悪の展開。そもそもディフェンスはまったくダメな今季なのだが、この日はオフェンス陣の調子もあがらない。Bostonのファンたちはしょんぼりと、でも有観客試合を楽しめるこの機会をフルに享受すべく売店のビールの列に並んでひたすら酔っ払う、というhappy sadなハーフタイムだった。

しかし、まさかのまさか、第3Q以降にはCelticsが奇跡の巻き返しを見せる。なんと第4Q終了間際には同点に追いつき、オーバータイムへもつれこむというプロの試合ではあまりお目にかからないような荒れた展開に。Celticsはオーバータイムにも勢いを保ち、143-140という点の取り合いを制して大勝利。その立役者はエースのJason Tatum、終わってみればこの日はキャリアハイ60得点の獅子奮迅の大爆発で、わたしとしても歴史的な偉業(!)の目撃者になったような気分で恍惚としてしまった。
まさかの勝利に興奮している他の観客のみなさん、特に赤ら顔のみなさんとハイタッチしながら会場を後にする。大逆転勝利のことは “comeback” と言うのだということを、やたら大きな声で “What a comeback! Right??” と繰り返し話しかけてきてくれた人のおかげで学んだ。
April 24
友人の運転でジャマイカ・プレインと呼ばれる南のほうの地域へ、アーノルド・アーボリータム(Arnold Arboretum)という樹木園に遠足に連れていってもらう。快晴の土曜日、多くの人が木々や花々を眺めながらピクニックするために、出てきている。COVID-19へのワクチン接種も進んでいるので、次第にではあるけれど、人間同士がどこかに集まって同じ方向を見て何かをする、という営為も当たり前のように回復されてきている。
いよいよ桜は満開でとてもキレイである。わたしの経験上の意見では、東京における…というか世界における最も桜が美しいスポットは早稲田の神田川沿いなのだが、ここの桜も色鮮やかで豪快で、このマサチューセッツの地の気候に合った咲き誇り方を学習しているのかもしれない。
帰路には、ブルックラインという地域にある日系スーパー、マルヨシさんに車で寄ってもらう。実はボストンに来てから、中国系スーパー、そして韓国系スーパーのH-Martにはよく行っていたのだが、日系スーパーに来るのははじめてであった。日本のインスタント麺なんかは中国系、韓国系スーパーでも買えるのだが、この店でしか目にしないものとして、梅入りのしそわかめとか、桜もちとか、そして精肉コーナーでは4ドル程度の砂肝のパックを発見して大喜び。その夜の食卓には、わたしの特製砂肝ガーリックバター炒めが並ぶことになった。
April 22
先の4月20日、伝説的なアメリカ人映画監督の Monte Hellman が亡くなった。1929年7月生まれの人なので、享年は91歳だ。訃報を聞いた際はコロナウィルスのためかも、と思ったが、自宅で転倒した後に入院してそのまま亡くなったとのこと。どことなく呆気ないが、それにしても長寿だなと驚かされもする。
Monte Hellmanといえば、日本での受容のされ方を振り返ると、真のシネフィル(映画マニア)以外は語ってはいけない聖域にいる映画作家のようであり、青春の大半を映画館通いで消耗し尽くすようなシネフィルの人たちを傍観していたようなわたしにとっては、敬して遠ざけねばならない対象のような気がずっとしていた。そういう作品を劇場で観る機会もそう頻繁にはなくて、代表作とされる『断絶』(Two-Lane Blacktop, 1972)、あとは『コックファイター』(Cockfighter, 1974)くらいしか観たことがないと思う。その他の作品を昔どこかで観たようなおぼろげな記憶もあるのだが、はっきりと思い出せない。ただ、いわゆるアメリカン・ニューシネマの監督たち、その諸作品とも連続している Monte Hellman のオフビートな美学というか、目の前にある出来事のプロセスを飄々と撮っていくスタイルがもたらす緊張感には、はっきりと魅了された。
たまたま渡米してから、立て続けに Monte Hellman 作品を観ることになった。きっかけは名画のリマスターを次々と発表するThe Criterion の チャンネルで 『銃撃』(The Shooting) と『旋風の中に馬を進めろ』(Ride in the Whirlwind)という、どちらも1966年制作の西部劇2作が入っていて、蜜に誘われるクワガタのように眠れない夜に観てしまったことだった。Hellmanの盟友である若き日の Jack Nicholsonは両作ともに出演していて、後者については脚本も書いている。すっかりと虜になった。アンチ-クライマックス、アンチ-勧善懲悪の不条理劇のようで、観賞後は爽快感など何もなくただただ奇妙な余韻が残る。
この日はMonte Hellman への追悼の意を込めて、『チャイナ9、リバティ37』(China 9, Liberty 37, 1978)という作品をAmazonプライムでレンタルして観た。1970年代後半には、そのあまりの売れなさからもうすでにアメリカ本国では映画製作ができなくなっていたHellmanが、イタリアに招かれてイタリア資本で撮ったカルト西部劇作品だ。これまた奇跡の傑作としか言いようのない刮目すべき低予算名画である。話はこんな感じだ。殺し屋が、鉄道会社に依頼されて、どうしても線路敷設のための立退きに応じない頑固な地主を殺しに来る。だが、互いにすねに傷を持つ似たような境遇の男たち、殺し屋と地主は友情を育みはじめる。そんな時に、地主の妻が殺し屋と恋に落ちてしまい、ただならぬ関係に。妻はある出来事をきっかけに、殺し屋と禁じられた愛の逃避行へ…と筋書きだけをなぞるとなんとも低俗な三角関係メロドラマのようだが、その中心的な3人以外にも、親族だったり通りがかりのサーカス団だったり、プロットの進行には直接関わらない魅力的な人間たちが続々と登場してくる。収拾のつかないカーニバルのように映画内の熱量が膨張する。
メロドラマの主役たちの周囲に、その他諸々の人たちによる奇妙であったり微笑ましかったりする共同体と関係性が出来上がっていくさまが描かれていて、そこにこそ心を奪われてしまう。わたしはいつだって名もなき人たちのちょっとshabby な群像劇が好きなんだな、と思う。
April 13
タフツ大学の図書館に。キャンパスに着いたら真っ先にPCR検査を受けに行く。鼻の粘膜を綿棒で採取する作業にすっかり慣れてきた。メドフォードでも桜が咲き始めている。キャンパスには試験前の学生たちもチラホラ、真剣そうな立ち話から聞こえてくる内容は fail (単位を落とす)しそうなんだけどどうすればいいか?など、東京の学生たちと変わらない。
April 8
ボストン美術館(Museum of Fine Arts, Boston。略称はMFA)へ。入館時間について事前予約をしておけば、まだ人数制限はあるが、自由に館内を見て回ることができる。企画展の Writing the Future: Basquiat and the Hip-Hop Generation 、わたしの興味と嗜好にぴったりな趣旨のもので、1970年代 の New York City における街中でのグラフィティパフォーマンスが、どのように1980年代の若いアフリカ系/カリブ系アーティストたちの美術作品、ファインアート運動へと展開されていくか、その流れや通底する美学を再構成して提示してくれる。日本でもよく知られているJean-Michel Basquiat の作品はもちろんだが、アーティスト/Hip-Hopミュージシャン Rammellzee の80年代以降の作品が生で見られることに感激した。
Afro-futurism とカテゴライズされる、アフリカ系作家/アーティスト/ミュージシャンたちの想像力のあり方または哲学がある。雑にまとめると、西洋中心の進歩的な歴史観、科学技術による人類の幸福の最大化、といったような考え方に対して、アフリカの各地域に古代から伝承される神話や文化的遺産をあえて現代の文脈に復活させ、それらが日夜更新されていく先端的テクノロジーと組み合わさるとどのような「ここにはないどこか、今にはない何か」(=未来)を実現するのか?とヴィジョンを提示してみせるような「未来主義」のことである。わたしも特講の授業でよく取り上げている。簡単にイメージできるように説明してしまうと「昔話」+「SF」というような感じであるし、最近のよく知られている例で言えば 映画 Black Panther (2018) の世界観だ。
Rammellzeeは1980年代以降 “Gothic Futurism” という独自の Afro-futurism 思想を練り上げていき、作品はその表現のためのメディアになっていった。今回の展覧会をきっかけに少し詳しく“Gothic Futurism” について調べてみると、これがまた異常に面白い。根本にあるのは「言語」とは抑圧である→その抑圧から「文字」を解放してやらねばならない→グラフィティ、レタリングはその解放の作業である…という命題だ。西洋文明の都合のいいように「文字」が収奪され、「言語」内の意味におさまりよくなるようにコントロールされている。この「文字」のほうを自由に組み合わせて、その形さえも自由に変容させて(つまり、Sを平準化されたきれいな形に描くのではなくて、ぐにゃっとした曲線を過度に強調していびつにするなど)、解き放つとしたらどうなるだろう?そんなRammellzeeは自ら Great Robber と称していたそうで、同題のグラフィティ/ペインティング作品が放つクールなエネルギーに揺さぶられた。
April 6
春の陽気を感じるお昼すぎ、どこからともなく何かが焦げるにおいが室内に充満してくる。庭に出てみて、近隣で火事でもあったのかと見回してみた矢先、空から真っ黒な物体が降り落ちてくる。真っ黒に焦げたパン。視線を上げてみると、アパートの最上階から煙がくすぶっている。その部屋の住人Jくんが、トースターでパンを焼き焦がしてしまい、それも尋常じゃない程度に数切れのパンを炎上させてしまったのものだから、反射的にか熟慮の末にか、とりあえずそれらの焦げパンを窓から外に放り投げたのだった。家事能力の低さおよび問題に直面した際の解決策の安易さ。非難したいわけではないが、そのような特徴を持つアメリカ成人はなかなかに多い。
火事にはならずに済んだ。しかし、煙はすぐには引かず、アパート棟内に少しづつ広がっていき、結果として火災警報器がけたたましく鳴ることに。アメリカのみではないと思うが海外の火災警報器のやかましさといったら凄まじく、こめかみに安物の目覚まし時計を埋め込まれたみたいな騒音だ。通りを歩く人に消防署への通報を促すために、正面玄関にあるサイレンも鈍い赤色の光を放って回りはじめてしまった。…とはいえ、ボストンのみなさん、どうせ誤作動かあるいは誰かがパンか肉でも焦がしただけでしょう、という感で、クールに無視して通り過ぎてくれる。とにかく大音量の警報機を止めないと、ということで2階に住むBさんが大家さんに電話をかけて警報機の止め方を教わる…ことができればよかったのだが、どうやらその意思疎通もうまくいかず、結局は大家さんがアパートに駆けつけてきてマニュアルを確認しながら警報を止めるまで、20分近くも金属音はとどろいていた。消防署に通報が行かなかったので、さらに輪をかけた大騒ぎにはならずに済んで良かった。みんなでホッと一息。引き金となった焦げパン張本人のJくんは、何ら悪びれるところもなかったようだ。