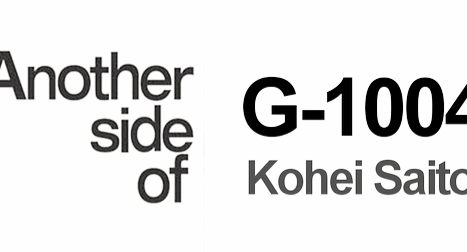未来は長く、先行きはただただ遠い。そんな当たり前をあらためて体感しつづける Stay Home の時間が、鋭い線というよりものっぺりとした面のように茫漠と広がっているこの頃ですが、先の4月17日に Bob Dylan は新曲 “I Contain Multitudes” を発表しました。この新曲リリースは、先月27日に発表された “Murder Must Foul” に続く、「ディラン、8年ぶりにオリジナルの新曲出していく」シリーズのいわば第2弾にあたります。 “Murder Must Foul” は、世界中が不安に凹んでいる2020年に、「1963年」と「John F. Kennedy大統領暗殺」という「歴史」を題材とした長尺の叙事詩だったのですが、今回の “I Contain Multitudes” で歌われている題材はいうなれば「自己」について、です。「自己」といっても、ただわたしはこう思う、こう感じる、という自分語りを担保するための何かではなくて、もう少し原理的かつ抽象的なレベルで、「自己」と画定しうるものはこれ一体何なんだろう?という問いとともにはじめて立ち上がってくるような何か、です。体験か、記憶か、他者との関わりか、一体何をもって今の「自己」が出来ていると言えるのか?今日のわたしと、昨日のわたしと、50年前(!)のわたしと、3年後のわたしと、何かこれこそが「わたし」と抽出できる同一性(この同一をidentityと呼ぶわけですが)なんであるのだろうか?
そこで、 “I Contain Multitudes” =「わたしは多数を含んでいる」というフレーズ。わたしというのは単数形ではなく、わたし自体がもはや複数形である。多くの記事やレビューがすでに真っ先に触れているように、このフレーズは19世紀アメリカの詩人 Walt Whitman の作品 “Song of Myself” の Section 51 から取られています。
Do I contradict myself?
Very well then I contradict myself,
(I am large, I contain multitudes.)
自己とは1より「大きい」、けれど同時に1として現れる、そんな矛盾した現象である。文学史の教科書で必ず読むお決まりの一節ではありますが、目にするたび、声に出して読み上げてみるたび、驚きと戦慄を背筋に覚える福音です。
ただ、このたび Dylan の新曲のタイトルとして、このパンデミックという広がりに誰もが身を縮めている2020年に “I Contain Multitudes”というフレーズを目にした時、わたしの脳裏には Whitman の詩情より先に、このわたしという生命体のなかにはまさに多数の微生物、細菌、ウィルスが「含まれている」という科学的に厳然たる事実のほうが浮かび上がりました。それもそのはず、 “I Contain Multitudes” というフレーズは、科学ライター Ed Yong が細菌と生命システムの複雑な相互依存的関わりについて書いた2016年のベストセラー本、I Contain Multitudes: The Microbes Within Us and a Grander View of Life のまさにタイトルにも引かれていて、そのことを覚えていたからです。生命の「自己」というものは、体内に含まれる大多数の「他者」である微生物や細菌との絶え間ない相互交渉を維持することを通して、システム化されて成りたっている–つまり、「他者」をそのシステムに含んでいない「自己」というものは、科学・医学的な観点からも、存在不可能なわけです。
老いてなお盛ん、老いてなお読書家の Dylan のこと、きっとこの Ed Yong の著作が念頭にあったのでは?と、一ファンとして大いに勘ぐっています。たぶん、いや絶対、そうでしょう。Dylan はなかなかどうして、特に21世紀に入ってからは、曲を発表するその時代のコンテクストにとっても敏感です。本人はそんなことをおくびにも出さないのですが、こっそりと友人への誕生プレゼントの包み紙に香水だったりあるいは時には毒の粉だったりをふりかけて忍ばせておくような施術が、とっても好きな人であることは間違いないのです。
そうして肝心の楽曲のほうは…甘くソフトな聴感でいながら音の配置される空間の奥行きが沼のように深いサウンドを、ここ数作のアメリカン・スタンダード曲カバーアルバム制作を通して完全に自家薬籠中のものとした最強のバックバンド(とにかく Donnie Herron のペダル・スティールをバンドに迎え入れたことこそが、2010年代以降の Dylan の大勝利でした)、そして鉄壁のスタジオワーク、もう言葉を失うほどに美しいバラードになっています。20世紀末から Dylan バラードのテンプレートになってきた、m7-5 のテンションコード使いもじんわりと沁みてきます。
すでに日本のソニーミュージックのサイトにも意訳が出ていましたが、わたしのほうでも、上述の解釈がよくも悪くも勝手に差し挟まれてしまった上での個人的な試訳/私訳をしてみたいと思いました。どんな歌とどんな「自己」なんだろう?わたしのココロのなかの Dylan はこんな感じの聖人であり、芸人であり、詩人であるというイメージを伝えられればいいな(多くの偉大な研究家の方々がいるなかで、そんなことお前がする必要ない、とも言われるでしょうけど…)と考えます。
今日も 明日も 昨日もまた
花は枯れるのが それが定め
ぴったりとついて来な バリナリー* に行くからね
来てくれなけりゃ おかしくなってしまう
髪の毛もいじれば 血闘もするし
私のなかにはたくさんのものがいるポー氏のごとき 告げ口心臓と*
壁のなかには 君の知り合いの骸骨
乾杯しよう 真実にも 口をついて出たことにも
乾杯しよう 君と寝る男に
風景画も描くし 裸体画も描くし
私のなかにはたくさんのものがある赤いキャデラックに 黒い口ひげ
指輪もキラキラ 光っているぜ
お次は何だい 何すればいい?
この魂ときたら 半分は君のものだけど
若い連中とだって どんちゃん騒ぎする
私のなかにはたくさんのものがいるアンネ・フランクみたいだし インディ・ジョーンズみたいだし
イギリスの悪ガキの ローリング・ストーンズみたいだし
ギリギリまで行きもすれば ぱったりと終わりにもする
失われたものが また大事にされる場所にだって行くウィリアム・ブレイクのように 「経験の歌」を歌う*
謝罪すべきことなど ありもしない
何もかもが 同時に流れているんだ
罪の大通りに生きていて
速い車をぶっ飛ばせば ファスト・フードも食べるし
私のなかにはたくさんのものがあるピンクのペダル・プッシャー* 赤いブルー・ジーンズ
すべてのカワイ子ちゃんたち すべての懐かしき
過去の人生で出会った女王たち
ピストル4挺に ナイフは2丁を持ち歩く
矛盾まみれの男 ただの気分屋
私のなかにはたくさんのものがいる欲張りな老ぼれ狼よ 私の心を打ち明けてやろうか
でも全部じゃなくて 嫌な部分だけを
そして君を下流に売り払ってやろう 頭に値札をつけて*
言えることはもうないさ こちとら生と死と同じベッドで寝てるんだ
消え失せてくれよ 膝にまたがってこないでくれ
その唇を近づけないでくれ道を開いておかなければ* 頭の中の道を
愛が置き去りにならないように 気をつけなくっちゃいけない
ベートーベンのソナタを奏でれば ショパンのプレリュードも弾いてみる
私のなかにはたくさんのものがある
*バリナリー:アイルランド中部の村、Ballinaleeのことらしいです。Dylanの歌の中には、「な、なんでこの地名?」というものがよく出てきて、研究者・ファンの間での謎解きゲームの格好の素材になるのですが、今回のバリナリーについてWeb上のあるフォーラムでは、19世紀のアイルランド人詩人 Anthony Raftery の詩 “The Lass from Ballynalee” への言及ではないか、という説がありました。ありえそうです。
*ポー氏:英語では “Got a tell-tale heart like Mr. Poe/ Got skeletons in the walls of people you know” となっているところで、Mr. Poeはもちろんここでは、19世紀のアメリカ人作家・詩人 Edgar Allan Poe (1809-1849)のことです。前半の “a tell-tale heart”=告げ口をする心臓とは、Poeの1843年の短編 “The Tell-Tale Heart” への言及で、後半の “skeletons in the walls”=壁のなかに骸骨というくだりは、これまたPoeの短編 “The Cask of Amontillado” (1846)内の「壁に人を生き埋めにする」エピソードへの言及になっていることは明らかです。どちらの作品もアメリカン・ゴシック文学の古典で、長さと気持ち悪さがちょうど良いので、Poe入門にもぴったりです。
*「経験の歌」:イギリス人詩人 William Blake の詩集 Songs of Innocence and of Experience (1794、『無垢と経験の歌』)への言及です。 “Songs of Experience” という後半部に収められている “The Sick Rose” は、いろいろな研究書で Dylan への大きな影響があるとされる、「愛と死」のイメージが鮮烈な詩です。
*ペダル・プッシャー:1950年代に大流行した女性用パンツの名称です。自転車がこぎやすいように丈が詰まっていて、ゆったりした形状。「アメリカ文化特講」で1950年代アメリカを数年前に教えたとき、自転車好きのわたしが嬉々として取り上げていたことを覚えている人がいたら嬉しいです。その流行に乗じて、50年代のロックンローラー Carl Perkins が出したシングル曲が “Pink Pedal Pushers” (1958)です。
*下流に売り払ってやろう:英語では “I’ll sell you down the river/ I’ll put a price on your head” となっていて、明らかに18-19世紀のミシシッピ川流域での奴隷売買を思わせる一節です。
*道を開いて:英語では “I’ll keep the path open”、最後にしっかりと Walt Whitman へのオマージュをここで繰り返しています。Whitman が生涯をかけて編纂しつづけた詩集 Leaves of Grass に収録されているものにおいて、”Song of Myself” とともに有名な作品が “Song of the Open Road” です。